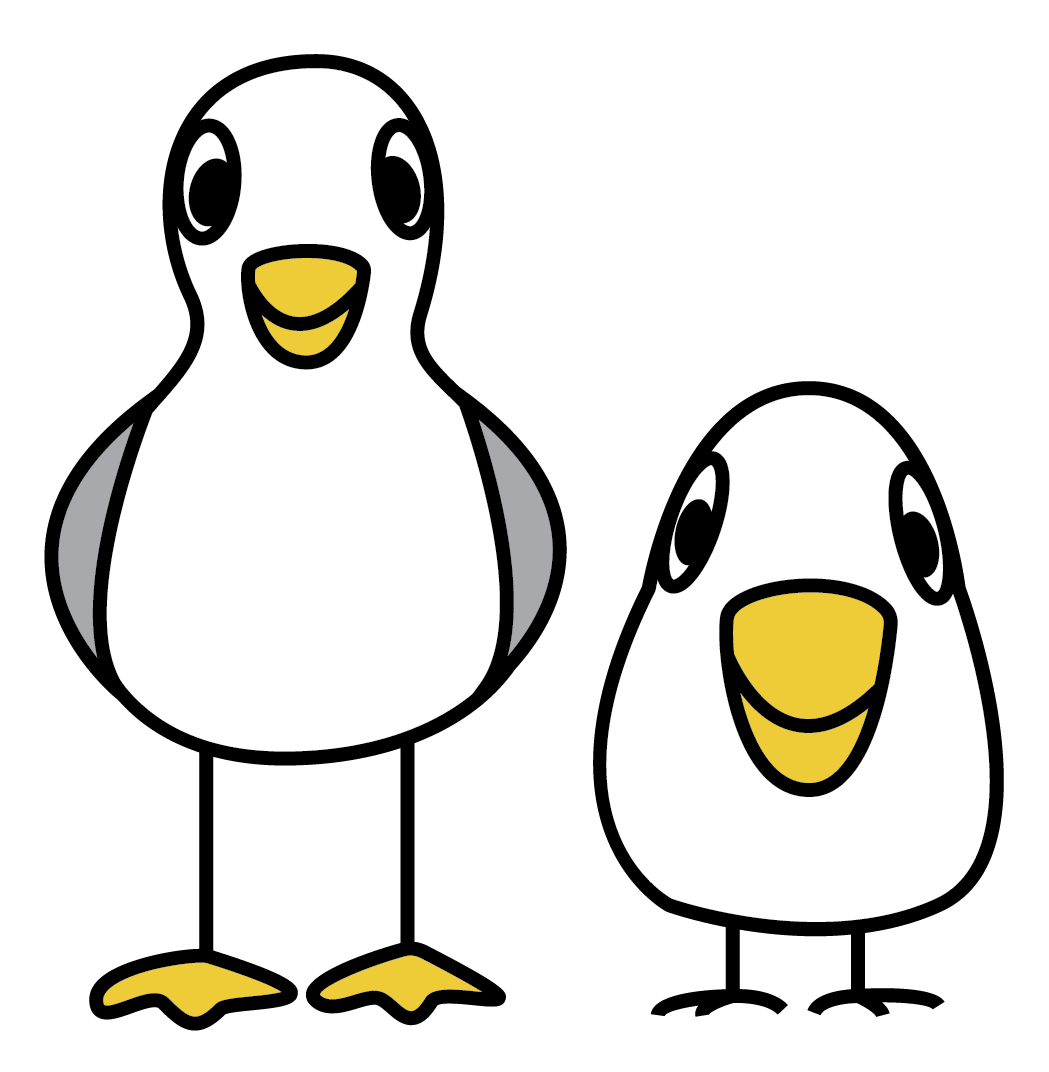Mori-Hoshi Institute of Literature
森星研究所
第1回 長山靖生「星新一と森鷗外 一切を越える紐帯」 SF史研究・文芸評論家 |
|
星新一と森鷗外に血縁関係があることはよく知られている。
森鷗外の妹・喜美子は森鷗外より二歳年上の人類学者・小金井良精に嫁いだが、彼女は星新一の母方の祖母にあたる。
良精・喜美子夫妻の次女せい(精)が大正一四年に星一に嫁ぎ、翌年に星親一(星新一の本名)が生まれた。
つまり星新一にとって森鷗外は大伯父だった。 両者の作品は、一見すると読みやすさへの配慮という点では逆方向のように見える。 星新一は常に読みやすさに配慮し、平易な言葉遣いを心掛けた。 対するに森鷗外は難漢字の使用も多く史伝小説を新聞連載した際には、一般読者を対象にするには難しすぎるとの非難が少なからず寄せられ、非常識とさえ言われたにもかかわらず、「非常識を恥じず、不見識を恥じる」と意に介さぬところがあった。 しかし森鷗外の文章も、たしかに現代人やあるいは明治人にとっても難しい表現だったかも知れないが、文体は明晰で簡潔だった。 無駄な形容がほとんどないのである。 むしろ森鷗外の場合、簡潔で的確な表現を求めたがために難字が多くなったのではないかと思われるところがある。 つまり「簡潔で適格」を求める本質において、両者は共通していたのである。 また人生の難事に当たっても坦々とした姿勢(もちろん内心の苦悩はただならなかっただろうが)や、密やかな反骨精神、そして何よりも品格の点において、両者はよく似ていた。 さらに父親の名誉を重んずる気持ちも共に強かった。 星新一は父・星一やその恩人である花井卓蔵を描いた評伝『人民は弱し 官吏は強し』や、父とかかわりの深かった人々を取り上げた『明治の人物誌』を書いている。 また大著『祖父・小金井良精の記』もある。 特に後者は森鷗外の『渋江抽斎』や『伊沢蘭軒』に通じる筆法が窺われる。 坦々と事実を積み上げていてくだけのように見えながら、深いところで情味があり、いくらか対象の姿に著者自身が重ねられた部分がある。 『人民は弱し 官吏は強し』には、『大塩平八郎』や「最後の一句」に通じる反骨精神もあるだろう。 そしてまた「カズイスチカ」に見られるような、親贔屓の微笑ましい要素も。 こうした要素は、果たして血脈によるものなのか、それとも作家としての理想を追求する厳正な精神的同族性だったのかは断定できないが、ここにより一切を越えるつながりがあることは確かだ。 星新一はショートショートの人と思われがちだが、長編評伝も味わい深くもっと評価されてよい。 有名な鷗外の遺書には〈死は一切を打ち切る重大事件なり ところで星新一と森鷗外をつなぐことになったのは、小金井良精と森鷗外の妹・喜美子の結婚だった。 ふたりの結婚話を進めたのは 賀古は医学校予科の寄宿舎生活以来の、森鷗外の親友だった。 欧米諸国に追いつくべく明治新政府は有為の人材育成を急いでエリート教育に力を注いだが、官立の新式学校への入学者は半ば旧幕旧藩の貢進生のようなところがあり、二十歳を過ぎた入学生も珍しくはなかった。 そんな中で森鷗外は異例の十二歳での入学。 二年先に入学していた賀古は、出合いの時には十九歳だった。 賀古は森鷗外の「ヰタ・セクスアリス」中の古賀 また賀古鶴所は千葉に別荘を建てた際、森鷗外にもどうかと誘い、これに応えて森鷗外も隣接する別荘を設けた。 それぞれ鶴荘、森鷗荘と名付けられ、中村 森鷗外の文筆は早くから高かったが、長州閥の元老で陸軍に絶大な力を持つ山縣有朋は文筆家を酷く嫌っていた。 その忌避を受けて森鷗外が出世コースから外れかけると、賀古は山縣に森鷗外の人物を熱心に推薦し、歌会で同席させるなど、折に触れてその軍医官人としての栄達に心を砕いた(賀古鶴所自身は早々に軍医を辞していたが、民間医師となりながらも戦時には率先して従軍するような愚直な愛国者だったため、山縣の信任が篤かった)。 鷗外が軍医の最高峰・軍医総監に就くのを側面から援助したものだった。 小金井喜美子の随筆「賀古氏の手紙」によると、結婚話に関する事情は〈私が小金井の人となりましたのは、賀古氏の世話なのでした。 兄は洋行中でしたから、帰った後にと両親は思っていましたのを、次兄の そっけない記述だが、喜美子への愛情が薄いわけではない。 森鷗外は自身の子供を深く愛し当時の父親としては異例なほど子供の為に気を配ったが、そうした情愛と配慮は弟妹にも向けられていた。 弟の場合、男としての自立の気概から兄の干渉が煩わしい場合もあるが(これは息子の場合もそうで、偉大な父に比べられることは息子には重い枷でもあった)、妹や娘にとっては偉大な兄・父から愛されている自信は、よい形で当人の人格を育成し、発揮されたように思う。 しかし森鷗外は日記や手紙では常に簡潔を旨としていた。 余分な言葉を書かない。 そんなところも星新一と共通している。 森鷗外が晩年、病臥していた頃の思い出として小金井喜美子はこんなことを書き残している。 〈ある日賀古さんだけが枕元においでになる。
そっと覗きましたら、 ちなみに森鷗外の遺言状では〈少年の時より老死に至るまで一切の秘密無く交際たる友〉〈唯一の友〉と書かれている。 そもそもこの遺言状自体、長男の森 賀古は森鷗外臨終のときも枕元におり、主治医が臨終を告げる一瞬前に、森鷗外につと顔を寄せて「では安らかに行きたまえ。」と告げ、部屋を出たという。 賀古は廊下で声なく泣いたのだろうか。 しかし間もなく戻って来て「デスマスクを取りたいと思いますが、お考えは。」と遺族に尋ね、てきぱきと作業に入った。 喜美子の次男(当時医科の学生)が手伝ったという。 さしあたっては忙しく何かをすることが、巨大すぎる死を耐える最適の方法だと、医師として多くの死を見送ってきた賀古は知っていたのかもしれない。 小金井喜美子は、晩年の賀古鶴所について〈兄が 賀古鶴所と小金井家の親交は、昭和六年に賀古が亡くなるまで続いた。 ここまで長々と賀古について述べてきたのには訳がある。 実は私が気になっているのは、大正一四年の星一と小金井せいの見合い、そして結婚決定に関して、何らかの相談を受けていたのではないかという点だ。 口喧しいところのある賀古は、毀誉褒貶喧しかった星一についてどう考えていたのか。 単純に考えれば反対しそうに思える。 しかし案外、官界を敵に回して一歩も引かない星一の姿に、亡友森鷗外と共通する気概を見ていたのかもしれない。 少なくとも結果的に小金井せいは星一に嫁したのだった。 そしてまた、それぞれの気概気骨を思うとき、星新一と森鷗外のつながりは血縁のみに由来するものではなく、飽くことなく真摯な自己探求を続けた文学者の、時空一切を越える紐帯だと思えるのだ。 2022年2月 |
© 2008 - 2025 The Hoshi Library