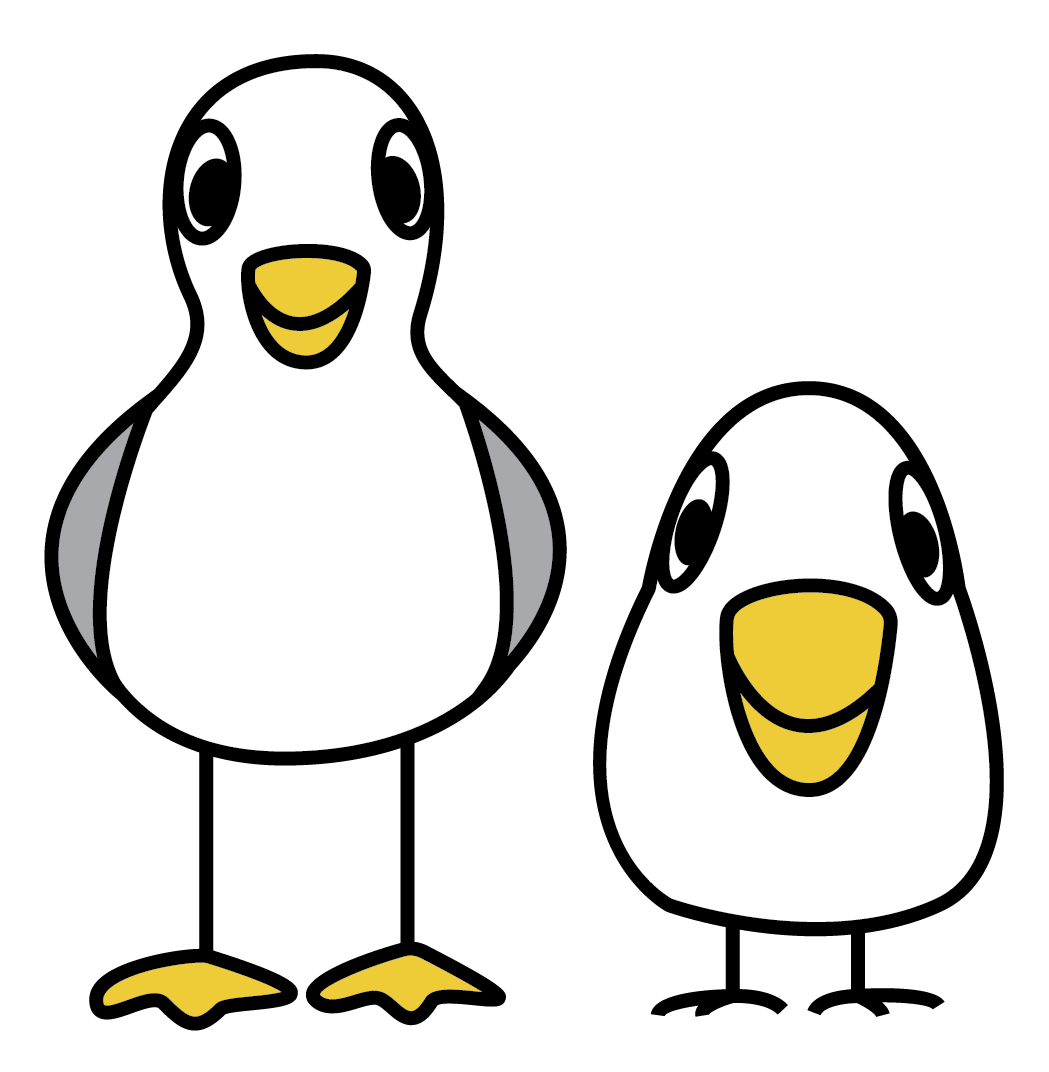Mori-Hoshi Institute of Literature
森星研究所
第2回 荒巻義雄「星新一と森鷗外 自己啓発する二人の巨人」 作家 |
|
1) 前置き 1960年代から70年代にかけての日本SF第一期を、間近に実体験できた者の一人として、星新一の存在は忘れがたい記憶である。 私は1933年(昭和8年)生まれだから、1926年(大正15年)生まれの星さんは七年も年上であり、いかにも風格があった。 ひと言ではうまい言い方が見付からないが、あの温顔を湛えた大柄な体躯で年下のわれわれを見守る大きな包容力に接して、わたしなどは安心したものである。 というのは、当時の日本SFは内外からの激しい批難に曝されており、自分がSF作家であると名乗ることすら、はばかられたからである。 だが、傍目でみても、星さんは飄々としており余裕があった。 SF作家に対する批難を独特のジョークで切り返す星さんに、同席のわれわれは笑い転げ、また精神的にも心理的にも救われたものである。 このゆとりがどこからくるのか、わたしはわからなかった。 星さん自身も、自らその出自を語ることもなかった。 わたしが、星さんの祖母が、日本近代文壇史に不滅の名を刻んだ森鷗外の妹であることを知ったのは、ずっとあとである。 だが、それがどのような意味を持つかを真摯に考えた者は、今のところ数多くはいないはずである。 実は、次女のマリナさんから依頼された本稿のテーマがこの問題の解明であるのだが、同時に文学者としての星新一再評価にも繋がるはずである。 2) 日本SF勃興期の事情 不幸にして勃興期の日本SFは、少数の愛好家たちに提供されるエンターテインメントであり、あるいはミステリーのサブ・ジャンル程度の扱いであって、わが国の伝統的文学からは無視されていた。 無理もない、SF小説という言葉すらまだ存在せず、サイエンス・フィクションや科学小説と呼ばれていたし、一方、SF内部でも文学的素養に乏しい理系や、たとえあったとしてもファンタジーの読者が主流の、小さな一ジャンルでしかなかったからである。 しかし、少なくとも、第一期日本SF作家クラブ会員の雰囲気はそうではなかった。 わたしはその末席を汚す一人であるが、大学一年のときには明治大正文学全集を全巻読破していたし、卒業年度には早稲田大学の図書館に通って、世界文学全集全巻を読了していた。 つまり、第一期作家には、もともと教養としての文学歴があり、それらに対する不満、言い替えれば、世界文学というよりは、当時のリアリズム文学一辺倒の日本文学へのアンチテーゼとして、自ら新しい文学を発見し、開発し、創造しようという暗黙の了解があった。 あれから半世紀が経ち、SFの現在はどうであろうか。 たとえば星新一賞の成功と定着、筒井康隆氏の2021年度日本芸術院賞受賞、一方、産業界ではSFプロトタイピングと言って、既存のSF小説が描く未来社会が存在すると仮定して、そのような社会になにが必要か、法整備はどうするかなどを研究するジャンルがすでに確立、実践されているのである。 思うにこうした発想は、シミュレーション小説の流行から立ち上がってきたと考えているが、さらに、視点を過去へ移して、SF小説が、星新一〜森鷗外のラインを探ることによって、その地下茎がわが国の文学史に接続するかどうかを思索することとしたい。 3) 森鷗外の妹 鷗外は1862年(文久2年)の生まれ、没年は1922年(大正11年)であるので、今年2022年がちょうど没後100年にあたる。 従って、1926年生まれの星新一は、生前の鷗外には会っていない。 また、新一は鷗外直系の子孫でもない。 鷗外の実妹が新一の祖母なのである。 この祖母の名は、嫁先の姓で小金井喜美子と言い、幼少時の新一は事実上、祖母に、直接、育てられたようである。 一方、鷗外と喜美子の文学の関係は、非常に深かったと言われる。 とすれば、当然、鷗外の著作はじめ、多くの書籍が祖母の手元にあったはずである。 そうした環境が、新一に深層心理に記憶として蓄積されていたであろうことは、十分、考えられる。 この小金井喜美子(1871年・明治3年〜1956年・昭和31年)は、『現代日本文学大事典』(明治書院)に名が載るほどであるから歴とした文学者であり、西洋文学の訳業で名声を得た。 また歌人であり、優れた随筆家でもあった。 なお、18歳で嫁いだ夫は、鷗外の先輩でドイツ留学から戻った人類学者の良精で、新一はこの人物について『祖父・小金井良精の記』を著している。 今回、本稿執筆のため、改めてネット検索した小金井喜美子は、明治期にあっては、まだ希有であった女性文学者で、近代詩の形成に多くの影響を与えた訳詩集『於母影』の共訳者五名に加わった唯一の女性でもあった。 なお、この『於母影』は、雑誌「国民之友」(明治22年)の夏期付録として刊行されたものである。 また平塚らいてうの『青踏』創刊にも関係するなど、わが国におけるフェミニズムあるいはジェンダー運動黎明期との関連で、今日、再評価されてよい先駆者の一人であるとも言える。 また晩年に発表された回想随筆集『森鷗外の系族』(昭和18年)や『鷗外の思ひ出』(昭和31年)は香気溢れる作品として評価され、同時に近代文学史研究の一次資料としても、重要視されているとのことである。 4) 森鷗外と日本文学史 一方、ドイツ留学から帰朝した鷗外が直面したのは、坪内逍遙(小説神髄)、二葉亭四迷(浮雲)、尾崎紅葉(二人女房)など、写実主義が主流であった明治文壇の傾向であった。 しかし、ゾラやフローベルに始まる写実主義の根幹には、内部必然的な自我の確立が前提であるはずなのに、わが国においては文学形式の移入が先行したために不完全燃焼に終わり、円熟にはいたらなかった。 これに対して敢然と論争を挑んだのが、エドゥアルト・フォン・ハルトマン(1842年〜1906年)の「無意識の哲学」で理論武装した鷗外で、逍遙との間で「没理想論争」(明治24年〜25年)が行われた。 このハルトマンは、ドイツの将軍の子息である。 一度は軍人の道を選んだが健康上の理由で断念、哲学の道へ進むのである。 鷗外の場合も、文学者でありながら軍医でもあるので、この共通点にシンパシーを抱いたのかもしれない。 なお、現在、鷗外研究の過程でハルトマンとの関連も研究されているようだが、要約するならば、ドイツ哲学を代表するヘーゲルの理性的世界観と、これに相反するショーペンハウアー(生の哲学)の両者を、アウフヘーベンさせたのが、ハルトマンの哲学である。 どうやら鷗外は、ハルトマンの「現象界に本質的世界が現れている」という主張に感銘したらしい。 かくして、写実主義に対抗する鷗外の浪漫主義文学が登場、観念的、思弁的文学が一世を風靡し、アンデルセン作の翻訳『即興詩人』(明治25年〜34年)はその浪漫的香気と典雅な訳文が原作以上と讃えられたのである。 5) 鷗外は新一に何を与えたか 以上、前置きが長くなった。 わたしは本稿のために、鷗外の作品を改めて再読してみた。 たとえば、『舞姫』『阿部一族』『山椒大夫』『高瀬船』など、いずれも新潮文庫などで読むことができる。(註1) 『舞姫』 鷗外の文壇処女作。 主人公の太田豊太郎は秀才、選ばれてドイツ留学を許される。 欧州の自由な空気に当たった彼の封建的官長への抵抗が始まる。 あたかも、鷗外自身をモデルにしているようである。 さらに失職と舞姫エリスとの恋。 二葉亭四迷『浮雲』と並び、〈近代的自我〉に目覚めた知的青年を登場させた画期的意義を持つ。 『阿部一族』 殉死という封建社会の武士のモラルが、いかに腐敗して人間性を傷つけ形骸化しているかを告発。 『山椒大夫』 自己否定、権威への盲目的服従など、鷗外本来の権威に対する反抗の精神とは正反対の人格が描かれている。 『高瀬舟』 不治の病に苦しむ弟を安楽死させた罪で、島送りになった主人公の身の上話を、同心が聞くという構成。 これらの代表作が星新一の作風になんらかの影響を与えた痕跡は見あたらないが、わたし個人的には、ショートショートよりもより優れて作家の才能と実力を感じさせる、祖父や父親の伝記文学との間に共通項があるように思う。 たとえば、史伝『渋江抽斎』であるが、この作品は弘前、津軽家の侍医で考証学者の渋江道純の伝記を克明に記述したものである。 この作品の特徴は史料を使い克明に再現したという意味で、当時としては新たなジャンルであった。 星新一が作家人生を賭けて開発、また1000編もの作品を完成させたショートショートへの情熱も、資料を駆使して書きあげられた『人民は弱し 官吏は強し』などの伝記も、もしかすると『渋江抽斎』に影響されたのかもしれない。 6) 鷗外と新一の実験精神 また『雁』という長編小説がある。 ある高利貸の妾、お玉が次第に自我に目覚め、散歩の道すがら顔をあわせる医学生の岡田に恋心を抱くようになる。 彼女は旦那の留守に岡田を家に招き入れようとするが、たまたま友人を伴っていたため、恋しい彼と二人きりになる機会が永遠に失われた。 翌日、岡田はドイツへ留学したからである。 なお、この題名は、岡田が不忍池で、偶然、投げた石に当たって雁が死んでしまった出来事から来ている。 つまり、この雁の運命のように、偶然で人生の岐路が決まってしまう不可知の何かを暗示しているのだ。 鷗外はこの仕掛けを、幼い頃に読んでいたものか、グリム童話の「釘」にちなんで「釘一本」と呼んでいたそうである。 つまり、一本の釘が抜けたために車輪がばらばらになって壊れるのと同じだという比喩として使っているのであって、『雁』では語り手の僕が、その日、下宿で出された鯖のみそ煮が嫌いだったので、蕎麦を食べるために岡田と外出したため、お玉は彼に声を掛けられなくなったという彼女にとっては予測不可能の偶然が、この作品のプロットの中に仕掛けられているのである。 前出の『舞姫』の構造にも実は仕掛けがあり、ベルリンが新市街と旧市街に分かれて、片方は日当たりが良く、片方が迷路状であるという都市の構造が、巧妙に作中に織り込まれて、それが主人公の太田の無意識を暗示し、ジュリア・クリステヴァが提唱する文学理論のインターテクステュアリティの一例とされているのだ。 この二例だけでも、鷗外という作家の小説作法は、極めて理論的であったことがわかる。(註2) 一方、星新一はどうか。 新一が祖母を経由して鷗外から学んだことは、オリジナリティーの追求であり、その発現がショートショートという文学上の一ジャンルの発見であった。 さらに、新一が目指したのは純粋小説であり、また作品の永遠性であって、そのため晩年には自作品の中から場所や時代を特定できるものは、固有名詞を含めて、極力、普通名詞化するという希有の実験を行った。 たとえば、星新一は「電話をかける」とは書くが、時代が特定できる「ダイヤルを回す」という表現は排除したのである。 こうした新一の単純化は、鷗外が近代小説でとった手法と正反対である。 鷗外は、主人公の行動を、時間と空間の座標軸に当てはめて詳述する手法を好んだ。(註2) 7) 結語 以上述べたとおり、鷗外と新一とには、作品の比較では類似性は見受けられない。 しかし、共に優れた伝記文学を著したという点では共通の才能が感じられるし、また鷗外の影響があったように思う。 人との接し方にも、年長の者が穏やかな視線で年下の者と接する家父長的な風格があった。 鷗外には観潮楼歌会等があったし、新一には日本SF作家クラブがあった。 日本SF作家クラブの初期(1970年前後)の雰囲気は、豊田有恒がいみじくも語ったように、あたかも梁山泊を思わせる自由闊達で非日常的な会話が楽しめる集まりであった。 われわれ後輩たちは、星新一と小松左京が交わす、高度に知的でかつ絶妙なジョークに圧倒され、また常識的な思考を破壊され、知らず知らずに、SF的思考を学ばされていたのである。 反面、その内面には、実父で星製薬を創建した星一氏の官僚との戦いを活写した『人民は弱し 官吏は強し』(新潮文庫)に見られるとおり、鷗外の精神と共通する権力に対する反骨精神が、確固たる信条としてあるようにも思われるのだ。 など、改めて思うのだが、もし星新一がいなかったとしたら、今日の日本SFはなかったかもしれない。 さらに、最後に付けくわえるならば、本稿は星新一研究の一助にすぎない。 どちらかというと星新一の評価に冷淡であったSF界の反省を込めて、新たな再評価が行われることを今後に期待して、拙稿の筆を置くこととします。 参考文献 註1 『現代日本文学大事典』 (明治書院) 1141ページ〜1146ページ 参照 註2 『文学テクスト入門』 (前田愛・著/ちくまライブラリー9) 95ページ、100ページ、125ページ、139ページ〜141ページ 参照 2022年6月 |
© 2008 - 2025 The Hoshi Library